エンベロープ
移動平均線の上下に一定の乖離率で引いた帯状の線。価格の行き過ぎを判断

なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
エンベロープっていうのはね、道路の両側にあるガードレールみたいなものなんだよ。真ん中に移動平均線という道があって、その両側に同じ幅で線を引いたものがエンベロープなの。
例えばね、普通は道の真ん中を走るけど、時々右や左に寄っちゃうことがあるでしょ?でもガードレールにぶつかったら戻ってくるよね。相場も同じで、上のラインや下のラインに触れたら、真ん中に戻ろうとすることが多いんだ。
このガードレールの幅は自分で決められるの。狭くすれば敏感に、広くすれば大きな動きだけを捉えることができるんだよ。
エンベロープを使えば、「今は行き過ぎかな?」「そろそろ戻るかな?」って判断の目安になるから、とっても便利なんだ!
つまりエンベロープは「相場の行き過ぎを教えてくれるガードレール」みたいなものだよ!
エンベロープは、まるでゴムひもの限界みたいなものなんだ。ゴムひもを引っ張ると伸びるけど、引っ張りすぎると元に戻ろうとする力が強くなるでしょ?
移動平均線を中心に、上下に同じ幅(例えば2%)の線を引くと、価格の伸びすぎ限界ラインができるの。上の線に触れたら「引っ張りすぎ!」、下の線に触れたら「縮みすぎ!」というサイン。
多くの場合、この限界に達するとゴムが元に戻るように価格も戻るんだ。これを知っていれば、行き過ぎた時に上手く売買できるかもしれないよ!

さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
エンベロープは、移動平均線を中心とした一定幅のバンドを表示するテクニカル指標なんですよ。移動平均線の上下に、設定した乖離率(通常1〜3%)で平行線を引くことで、価格の行き過ぎを視覚的に判断できます。統計的に価格は移動平均線に回帰する性質があり、その特性を利用した逆張り指標として活用されています。
エンベロープの設定は相場のボラティリティに応じて調整が必要です。為替なら1〜2%、株式なら2〜3%、ボラティリティの高い銘柄なら3〜5%が一般的です。期間は20日や25日がよく使われますが、取引スタイルに応じて調整します。重要なのは、過去のデータで最適な乖離率を検証することです。
活用法は主に2つあります。逆張り手法では、上限タッチで売り、下限タッチで買います。一方、順張り手法では、バンドを明確に突破した方向にエントリーします。また、バンドの傾きでトレンド判断も可能で、上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドと判断できます。シンプルながら、使い方次第で多様な戦略が可能な指標なんですよ。
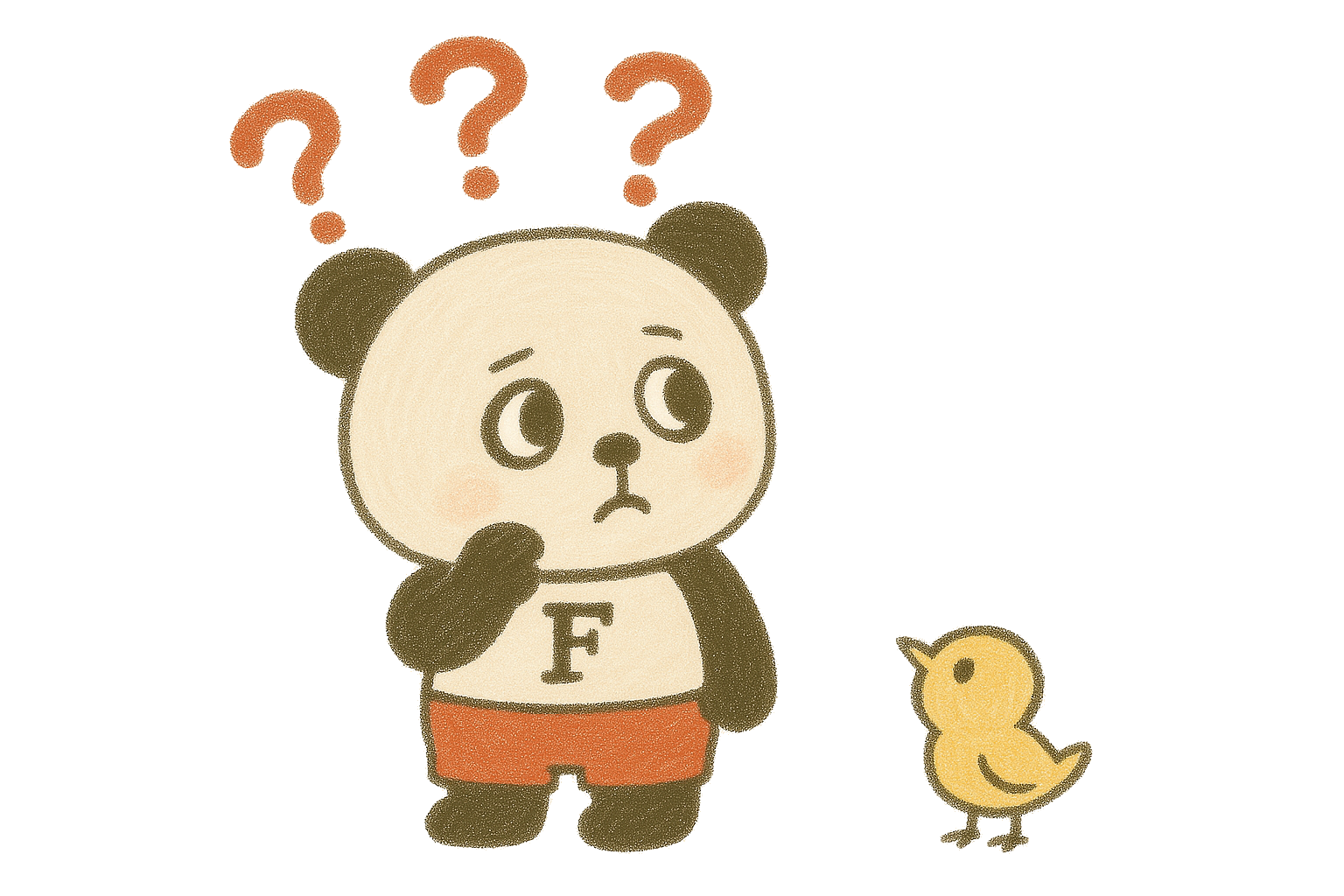
エンベロープに関するQ&A
よくある質問と回答
