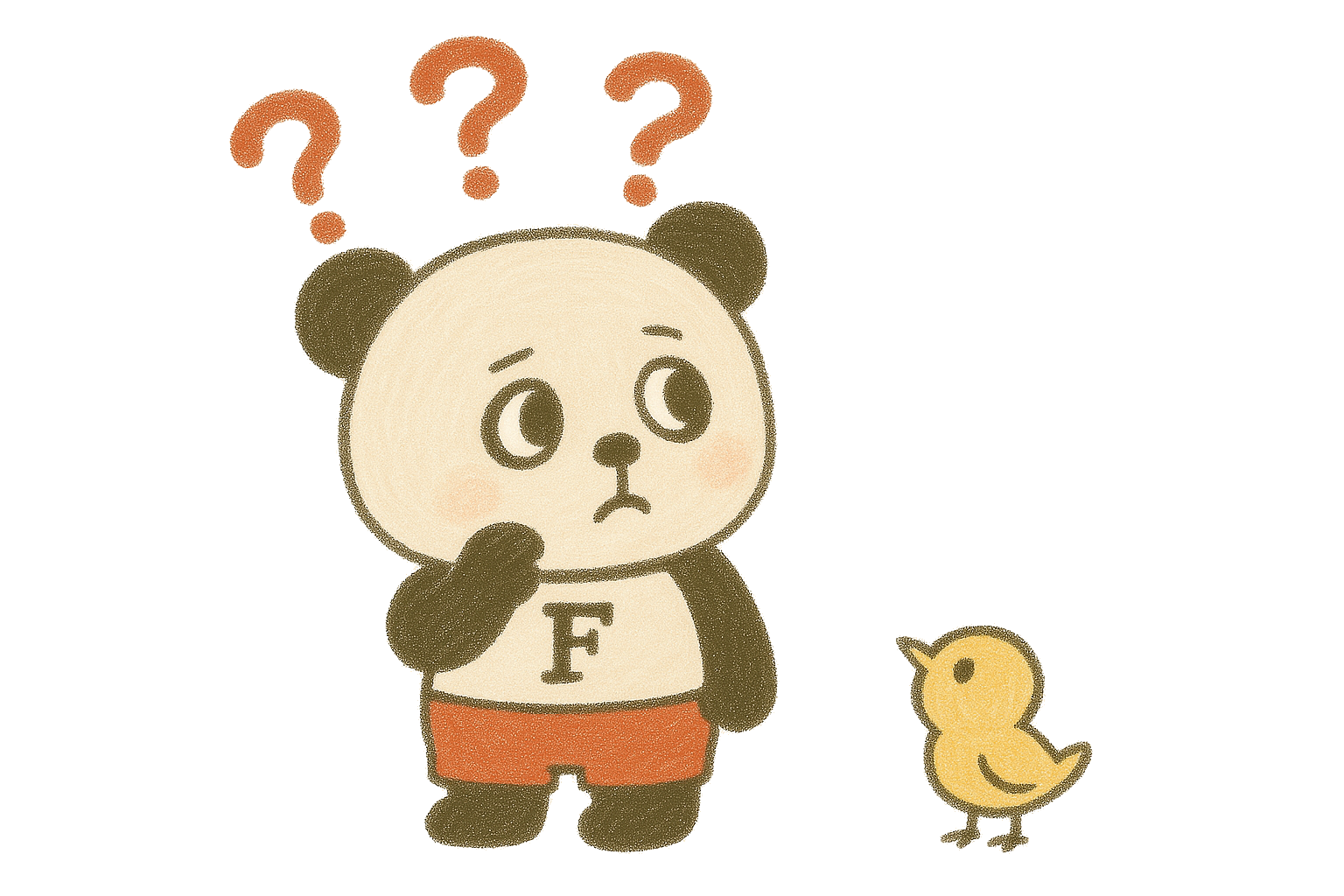わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01 なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
落ちるナイフっていうのはね、すごく危ないことをしちゃダメっていう意味の言葉なんだよ。本物のナイフが上から落ちてきたら、絶対に素手で掴もうとしちゃダメでしょ?手を切っちゃうもんね。FXでも同じで、値段がどんどん下がってる時に買うのは危ないんだよ。
例えばね、滑り台を滑ってる友達を途中で止めようとしたら、一緒に滑っちゃうでしょ?それと同じで、下がってるものを止めるのは難しいんだ。だから、完全に止まってから触った方が安全なんだよ。
でもね、大人の中には「今が安いかも!」って思って、落ちてる途中で買っちゃう人もいるんだ。でも、もっと下がっちゃうこともあるから、とっても難しいんだよ。だから、この言葉は「慌てないで、よく考えてね」って教えてくれてるんだ。
つまり下がってる最中に手を出すと痛い目に遭うかもしれないんだよ!
落ちるナイフを掴もうとするとね、どんなに気をつけても怪我しちゃう可能性が高いんだよ。だから、賢い人は床に落ちて止まるまで待つんだ。
FXでも同じで、値段が急に下がってる時は、どこまで下がるか誰にも分からないんだよ。「もう下がらないだろう」って思っても、もっともっと下がっちゃうこともあるんだ。だから、しっかり止まったのを確認してから行動する方が安全なんだよ。これが「落ちるナイフ」の教えなんだ。

STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
「落ちるナイフはつかむな」という相場格言は、急落中の相場で安易に買いを入れることの危険性を警告しているんですよ。文字通り、落下中のナイフを素手でつかもうとすれば大怪我をするように、暴落中の相場で底値を狙って買いを入れると、大きな損失を被る可能性が高いということなんです。
この格言が示唆しているのは、相場の底は誰にも分からないという真理です。「もうこれ以上は下がらないだろう」と思って買っても、相場はさらに下落を続けることがよくあります。特にパニック売りが発生している時は、理論的な適正価格を大きく下回ることも珍しくありません。感情的な売りが売りを呼ぶ悪循環に陥ると、予想をはるかに超える下落となることもあるんです。
では、どうすればいいのか。答えは「床に落ちて転がるのを待つ」ことです。つまり、下落が止まり、底打ちのサインが確認できるまで待つということですね。具体的には、ダブルボトムの形成や出来高を伴った反発など、明確な転換シグナルを確認してからエントリーする方が安全なんです。確かに底値からは買えませんが、大きな損失を避けることができます。
関連用語をチェック!
暴落 相場が急激に大幅に下落すること。落ちるナイフの状況を生み出す 底値買い 相場の最安値付近で買うこと。落ちるナイフを掴もうとする行為 ナンピン 下落中に買い増しして平均取得価格を下げること。落ちるナイフで危険な手法 セリングクライマックス 売りが最高潮に達すること。ナイフが最も速く落ちている状態
逆張り トレンドに逆らって取引すること。落ちるナイフを掴むのは典型的な逆張り 順張り トレンドに沿って取引すること。落ちるナイフを避ける安全な手法 キャッチ 下落中の相場で買うこと。falling knifeをcatchするという英語表現から
底打ち 下落が止まって上昇に転じるポイント。ナイフが床に落ちた状態
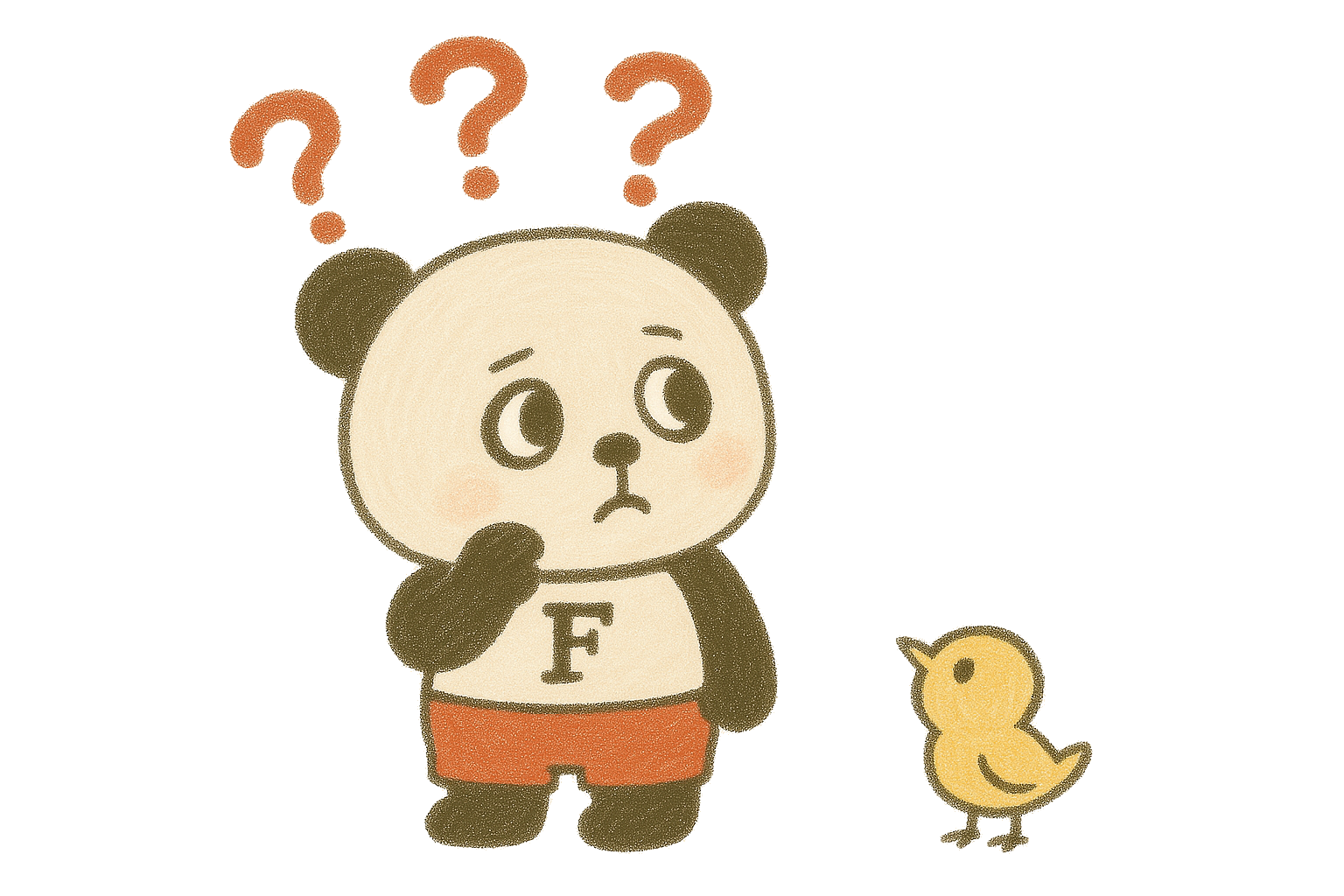
STEP 03 落ちるナイフに関するQ&A
よくある質問と回答
まず
冷静に損切りラインを設定することが重要です。既に
含み損が出ている場合でも、さらなる損失を防ぐためにストップロスは必須です。その上で、
ポジションサイズを確認し、リスクが大きすぎる場合は一部を
損切りすることも検討しましょう。感情的にならず、機械的にリスク管理を行うことが、被害を最小限に抑える鍵となります。
急激な下落と出来高の急増が主な特徴です。通常の調整とは違い、パニック的な
売りが出ている時は、
ローソク足が長い陰線を連続で形成し、出来高も普段の数倍になります。また、
ニュースやSNSでの悲観的な論調が急増するのも特徴です。テクニカル的には、
ボリンジャーバンドの下限を大きく割り込むような動きも、落ちるナイフの可能性を示唆します。
「安く買えるチャンス」という心理が働くからです。急落を見ると、バーゲンセールのように感じて、つい手を出したくなるんです。また、
以前の高値を知っていると、「こんなに安いはずがない」という固定観念も影響します。さらに、他の人より先に底値を当てたいという競争心理も、この危険な行動を誘発する要因となっています。
必ず反発するとは限りません。一時的な
リバウンドはあることが多いですが、それが本格的な上昇につながるかは別問題です。むしろ、
下落トレンドが継続することも多いんです。企業の倒産リスクや、経済危機などが背景にある場合は、さらに下落が続く可能性もあります。だからこそ、安易に手を出さずに、状況を見極めることが大切なんです。
経験豊富なプロでも基本的には避けます。ただし、十分なリスク管理のもとで、小さな
ポジションで試し
買いをすることはあります。その場合も、
明確な損切りラインを設定し、総資金に対するリスクを限定します。また、
ファンダメンタルズ分析に基づいて、明らかに売られ過ぎと判断できる場合に限定されることが多いです。
数時間から数か月まで様々です。
フラッシュクラッシュのような瞬間的な暴落なら数分から数時間で終わることもありますが、金融危機のような構造的な問題が原因の場合は、
数か月から年単位で下落が続くこともあります。2008年のリーマンショックでは、多くの資産が1年以上下落を続けました。期間の予測は困難なので、憶測で動かないことが重要です。
明確な底打ちサインが出てからが基本です。具体的には、
ダブルボトムやトリプルボトムの形成、
出来高を伴った大陽線の出現、
移動平均線の
ゴールデンクロスなどです。また、
市場のセンチメントが極端に悲観的になり、誰も
買いたがらない時が、逆に底値圏であることもあります。ただし、これらのサインが出ても、小さな
ポジションから始めることが賢明です。
「頭と尻尾はくれてやれ」という格言があります。これは、最
高値での
売りや最
安値での
買いを狙わず、確実な中間部分で利益を取れという教えです。また、
「三空叩き込みに買い向かえ」という格言もありますが、これは十分な下落の後での買いを推奨するもので、落ちるナイフとは正反対の教えです。どちらも、極端な価格での取引を避ける知恵を説いています。