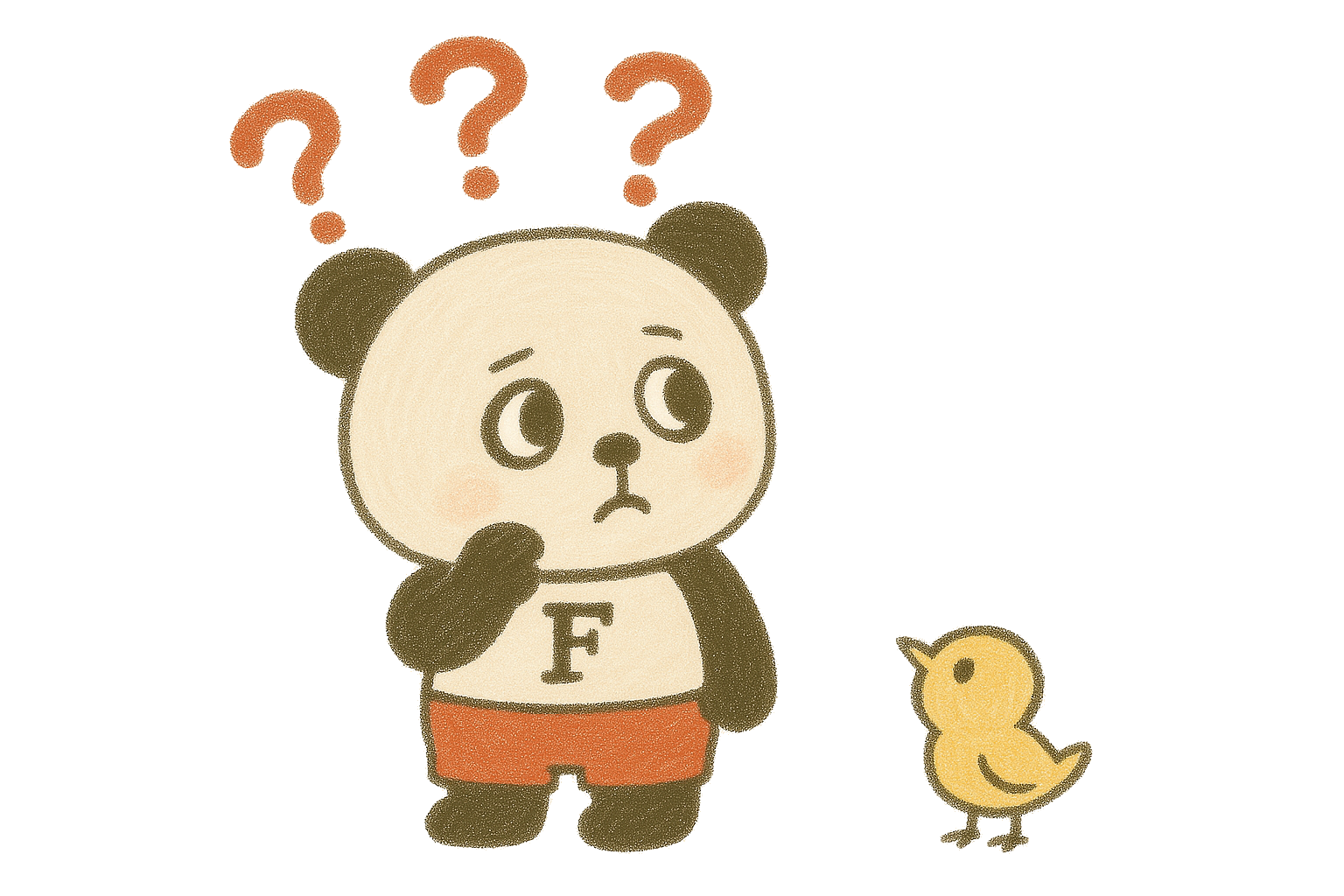わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!
金融引き締め
中央銀行が金利引上げ等で過熱経済を冷やす政策

STEP 01 なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
金融引き締めっていうのはね、国の偉い人たちが「みんながお金を使いすぎないようにするブレーキ」をかけることなんだよ。
たとえばね、お祭りでみんなが綿あめを買いすぎて、綿あめ屋さんが「もう作れない!」ってなったら困るでしょ?だから、綿あめの値段を上げて、みんなが買いすぎないようにするんだ。
金融引き締めも同じで、お金を借りにくくしたり、預金の利息を増やしたりして、みんながお金を使いすぎないようにするんだよ。
景気が良すぎると、物の値段がどんどん上がっちゃう(インフレ)から、ちょうどいい具合にするために使う方法なんだ。
車でいうと、スピードが出すぎた時にブレーキを踏むのと同じだね。安全運転のために必要なことなんだよ。
つまり金融引き締めは経済の使いすぎを防ぐブレーキだよ!
金融引き締めは、経済という車にブレーキをかけることなんだよ。
君が自転車に乗っていて、下り坂でスピードが出すぎたら怖いでしょ?そんな時はブレーキをかけて、安全なスピードに戻すよね。経済も同じで、みんながお金を使いすぎて物の値段が上がりすぎると困るんだ。
だから中央銀行の人たちは、金利を上げることでブレーキをかけるんだよ。すると、お金を借りるのが大変になって、みんな慎重にお金を使うようになる。
貯金箱に入れたお金がたくさん増えるようになるから、無駄遣いしないで貯金する人も増えるんだ。こうやって、経済を安定させているんだよ。

STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
金融引き締めは、中央銀行が過熱した経済を冷却するための政策手段なんですよ。インフレーションが加速したり、資産バブルの兆候が見られる時に実施されます。主な手法は政策金利の引き上げで、これにより資金調達コストが上昇し、経済活動にブレーキがかかります。
具体的なメカニズムとして、金利上昇により借入需要が減少し、企業の設備投資や個人の住宅購入が抑制されます。また、預金金利も上昇するため、消費より貯蓄が選好されるようになります。中央銀行は保有資産の売却(量的引き締め)を併用することもあり、市場から資金を吸収します。
FX市場では、金融引き締めは通貨高要因となります。金利上昇により、その通貨の投資魅力が高まるからです。米FRBの利上げ局面ではドル高が進行することが多く、キャリートレードの巻き戻しも発生します。ただし、過度な引き締めは景気後退リスクもあるため、中央銀行は慎重な舵取りが求められるんですよ。
関連用語をチェック!
金融緩和 金利引下げ等で景気刺激する引き締めと正反対の政策 利上げ 政策金利を引き上げる金融引き締めの代表的手段
インフレ抑制 物価上昇を抑える金融引き締めの主要目的
タカ派 金融引き締めに積極的な政策スタンス
量的引き締め(QT) 中央銀行が保有資産を売却し資金を吸収する政策
過熱経済 需要超過でインフレ圧力が高まっている経済状態
景気後退 過度な引き締めがもたらす経済活動の縮小リスク
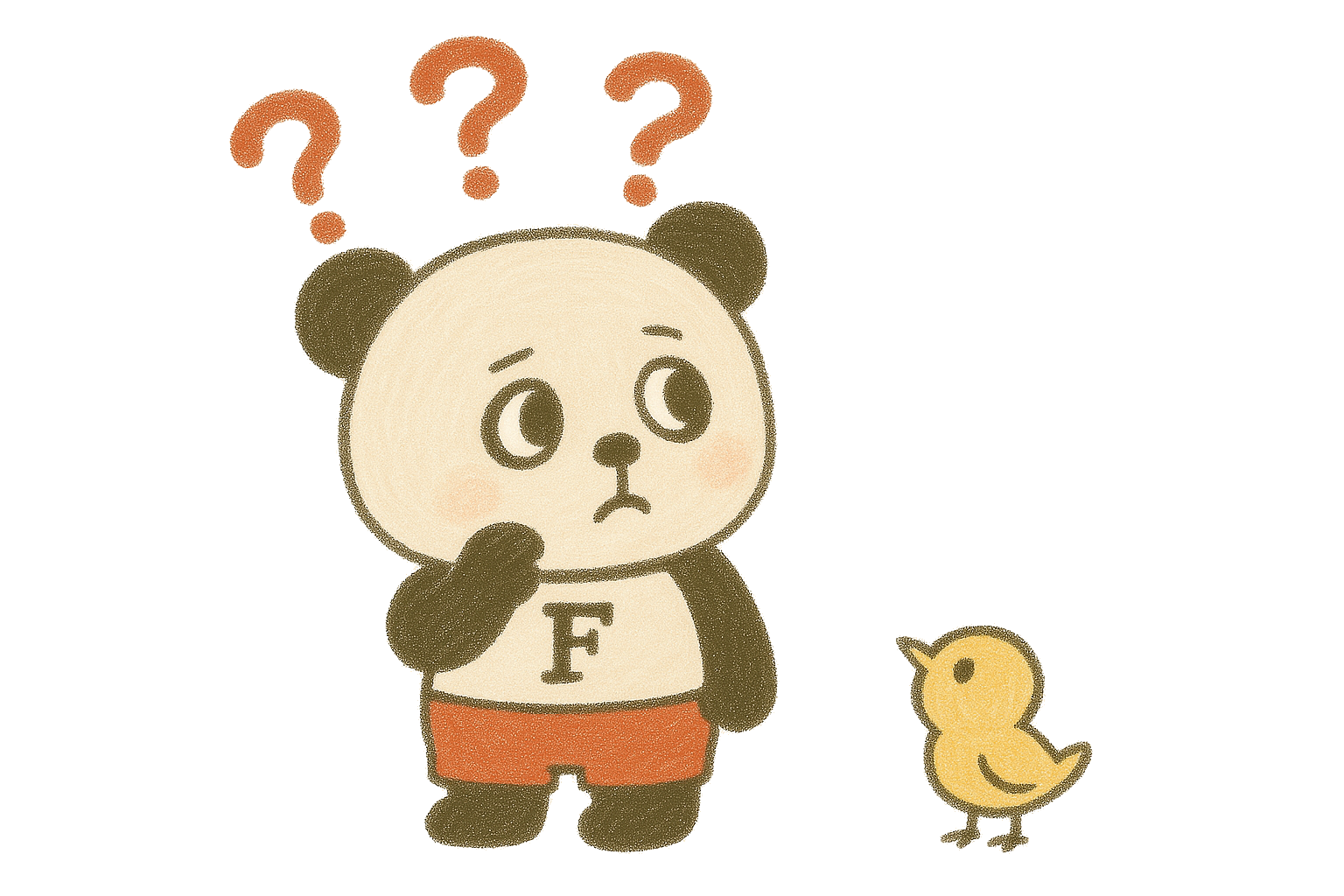
STEP 03 金融引き締めに関するQ&A
よくある質問と回答
主に
インフレ率が目標を上回る時に実施されます。多くの
中央銀行は2%程度のインフレ目標を設定しており、これを大幅に超えると引き締めを検討します。また、
資産価格の急騰や信用の過度な拡大も引き締めのサインとなります。
経済指標を総合的に判断して決定されます。
基本的に
通貨高要因です。
金利が上昇すると、その通貨で運用する魅力が増し、海外から資金が流入します。ただし、引き締めが
景気を過度に冷やすと判断されれば、逆に通貨安になることも。市場の期待と実際の政策のギャップも重要な変動要因です。
量的緩和(QE)の
巻き戻し政策です。
中央銀行が保有する国債等を売却または償還時に再投資しないことで、市場から資金を吸収します。利上げと併用されることが多く、より強力な引き締め効果があります。FRBは2017年からQTを開始しましたが、市場への影響を考慮し
段階的に実施しています。
最大のリスクは
景気後退(リセッション)です。急激な引き締めは企業倒産や失業増加を招く可能性があります。また、新興国では資金流出による通貨危機のリスクも。住宅ローン
金利上昇による
不動産市場の冷え込みも懸念材料です。
中央銀行は慎重なバランス取りが求められます。
タカ派は金融引き締めに積極的で、インフレ抑制を重視する立場です。
ハト派は
金融緩和を支持し、雇用や成長を重視します。
中央銀行の政策決定会合では、両派の議論が交わされます。
中立派も存在し、経済状況に応じて柔軟に判断します。
方向性が正反対です。緩和は「アクセル」、引き締めは「ブレーキ」と例えられます。緩和は
金利を下げて資金供給を増やし、引き締めは金利を上げて資金を吸収します。景気循環に応じて使い分けられ、
適切なタイミングでの政策転換が経済の安定に重要です。
金融緩和が正反対の政策です。引き締めが経済のブレーキなら、緩和はアクセルに相当します。景気が悪い時は緩和、過熱している時は引き締めという形で、経済状況に応じて使い分けられます。この政策の切り替えを
金融政策の正常化と呼ぶこともあります。
インフレが目標水準に収まるまで継続されるのが基本です。ただし、経済への副作用も考慮する必要があり、景気後退の兆候が見られれば政策転換もあり得ます。市場は常に「利上げ打ち止め」のタイミングを予測しており、
中央銀行の声明に注目が集まります。