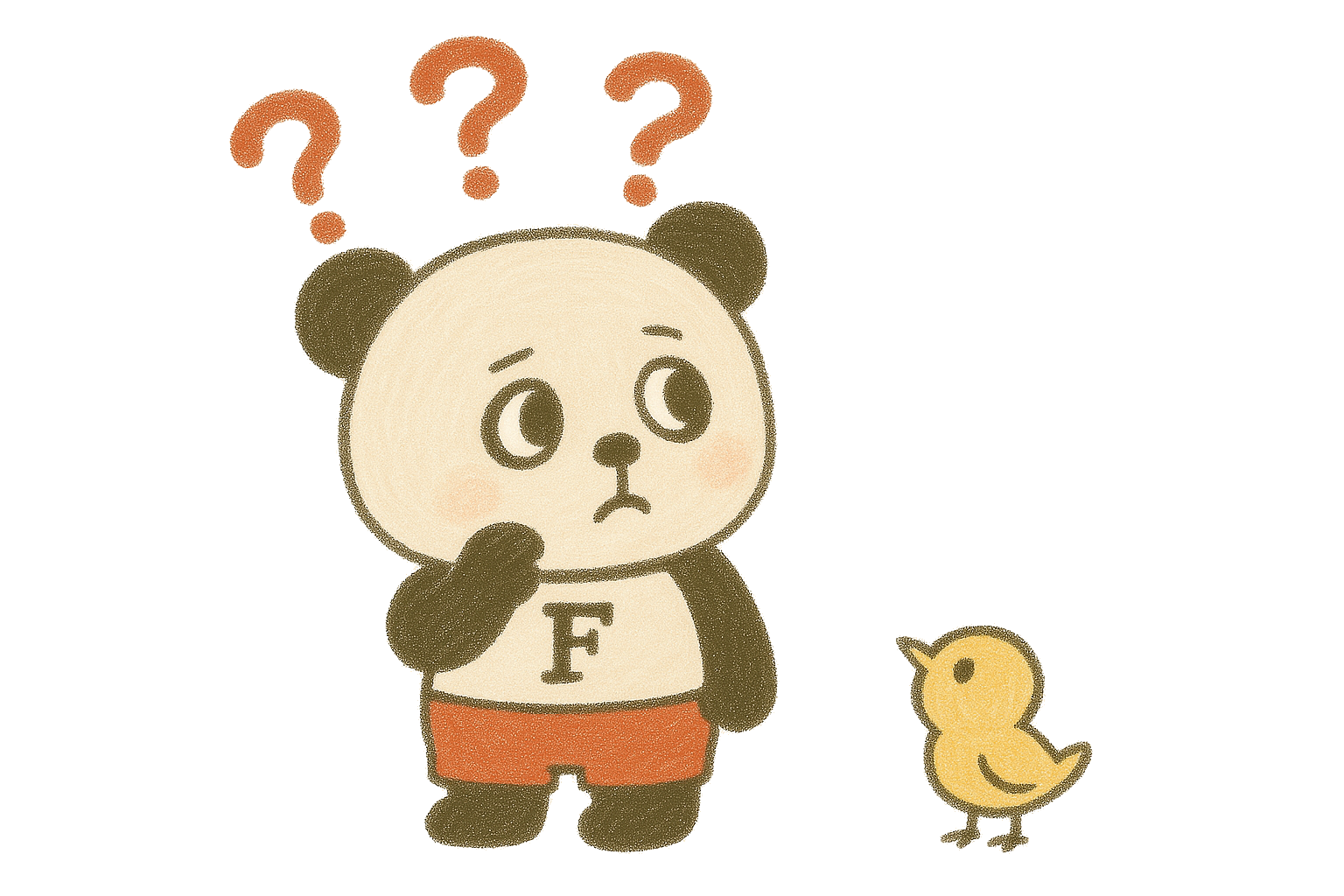わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語!

STEP 01 なんとなく理解しよう!
5歳でもわかる超かんたん解説
プロスペクト理論っていうのはね、人は得することより損することの方がずっと嫌いっていう心の仕組みのことなんだよ。
例えばね、100円もらえる嬉しさと、100円なくす悲しさを比べると、なくす悲しさの方が2倍くらい大きく感じるんだって。不思議でしょ?
だから、お小遣いを貯めている時に10円もらったら「やった!」って思うけど、10円落としちゃったら「最悪だ〜!」ってすごく悲しくなるよね。(大人も同じ気持ちになるんだよ)
この理論のせいで、損しそうな時は「もう少し待てば戻るかも」って希望を持っちゃうんだ。でも、それが失敗の原因になることも多いんだよ。
つまりプロスペクト理論は「損するのが大嫌いな心の法則」みたいなものだよ!
プロスペクト理論は、ゲームで負けた時の気持ちで説明できるんだ。
じゃんけんで勝って飴を1個もらった時と、負けて飴を1個取られた時、どっちの印象が強く残る?きっと取られた時の方が悔しくて忘れられないよね。
人の心は、「失うこと」をとても怖がるようにできているんだ。だから、ゲームで負けそうになると「まだ大丈夫、次で勝てる!」って思い込んで、結果的にもっと大きく負けちゃうことがあるんだよ。これがプロスペクト理論の罠なんだ!

STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう!
もっと詳しい本格解説
プロスペクト理論は、人間が利益と損失を非対称的に感じる心理的傾向を説明する理論で、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって提唱されたんですよ。
この理論の核心は、同じ金額でも、利益よりも損失を約2.25倍強く感じるということです。例えば、1万円を得る喜びよりも、1万円を失う苦痛の方がはるかに大きく感じられます。これにより、FXトレードでは「損小利大」の逆である「損大利小」の行動パターンに陥りやすくなります。(利益はすぐに確定したがり、損失はなかなか確定できないのです)
FXトレードにおける具体的な影響として、含み益が出るとすぐに利益確定してしまい、含み損は「いつか戻る」と期待して塩漬けにしてしまう傾向があります。また、連敗後には取り返そうとしてリスクの高い無謀なトレードをしてしまうこともあります。これらの行動は全て、プロスペクト理論で説明できる非合理的な判断なんですよ。克服するには、明確なルールを設定し、感情を排除した機械的な取引を心がける必要があります。
関連用語をチェック!
認知バイアス 判断を歪める心理的な偏り。プロスペクト理論も認知バイアスの一種
行動経済学 心理学を取り入れた経済学。プロスペクト理論の基礎となる学問
アンカリング 最初の情報に引きずられる心理。エントリー価格へのこだわりなど 損小利大 損失を小さく、利益を大きくする理想的なトレード
感情的トレード プロスペクト理論に支配された非合理的な取引
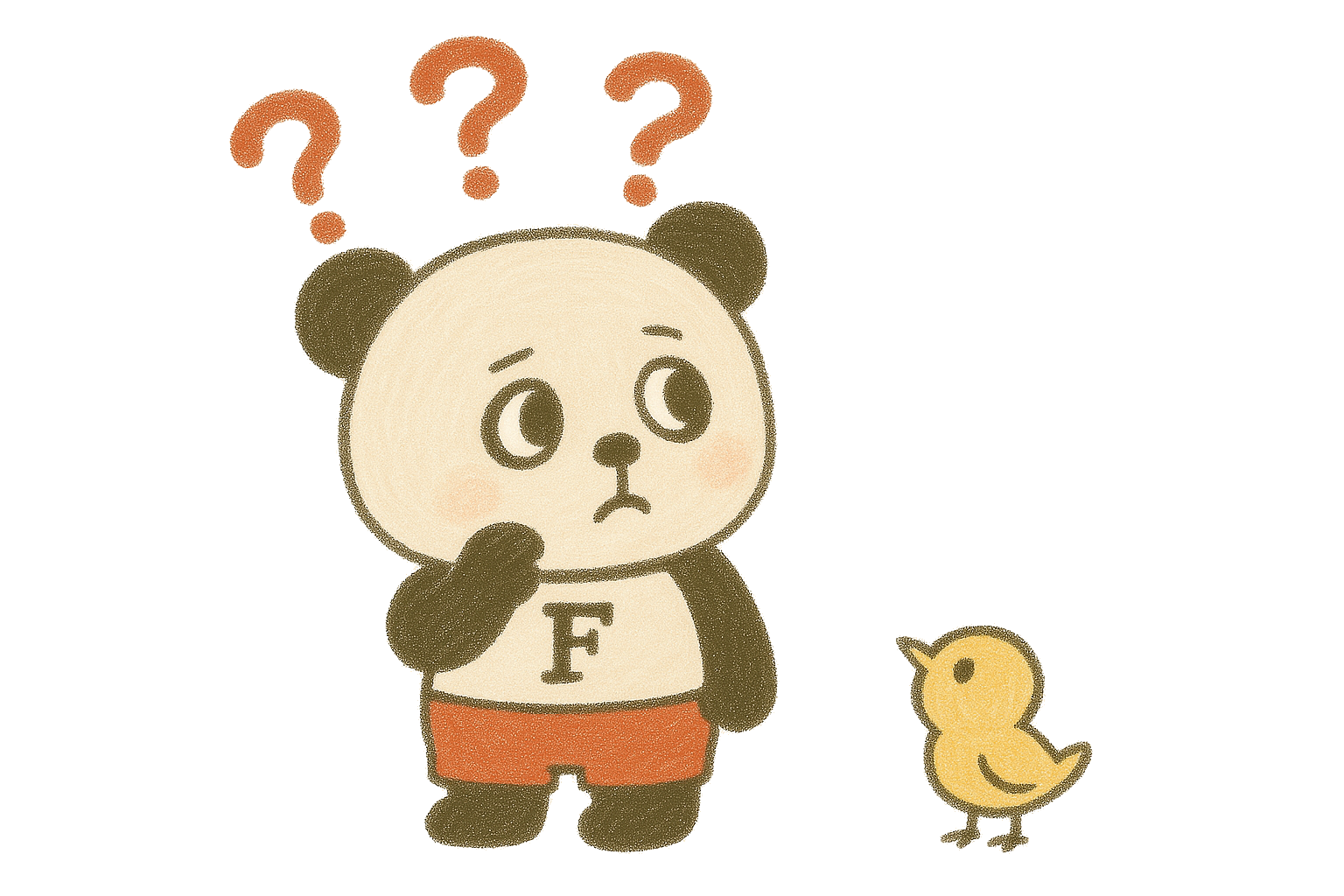
STEP 03 プロスペクト理論に関するQ&A
よくある質問と回答
プロスペクト理論によると、
損失を確定させることは心理的に非常に大きな苦痛だからです。
含み損の状態なら「まだ負けていない」と自分に言い聞かせられますが、
損切りすると敗北が確定してしまいます。また、
「もう少し待てば戻るかも」という根拠のない希望にすがってしまうのも、
損失回避バイアスの表れです。
(宝くじを買う時の「もしかしたら」と同じ心理です)この心理を克服するには、
エントリー時に必ず損切りラインを決めて、機械的に実行することが大切です。
プロスペクト理論では、
利益を失うことへの恐怖が、利益を伸ばす欲望を上回ると説明されています。少しでも
含み益が出ると「今のうちに確定しないと無くなるかも」という不安に駆られ、早めに決済してしまいます。これは
「確実な利益」を選ぶ傾向の表れです。
(鳥は手の中の一羽の方が、茂みの中の二羽より価値があると感じるのです)また、過去に含み益を失った経験があると、この傾向はさらに強まります。
利益目標を事前に設定することで改善できます。
プロスペクト理論の影響を克服するには
「ルールの明確化」と「自動化」が鍵となります。まず、
エントリー前に利益確定と
損切りの水準を明確に決め、
OCO注文などで自動化します。次に、
トレード日記をつけて、感情的な判断を客観的に振り返る習慣をつけます。また、
資金を失うことを前提とした資金管理を行い、精神的プレッシャーを軽減します。
(「このお金はもう無いもの」と考えると楽になります)定期的な休憩も、感情をリセットするのに有効です。
連敗時は
プロスペクト理論の影響が最も強く現れる危険な状態です。損失を取り返そうとする焦りから、
通常より大きなリスクを取る「リベンジトレード」に走りやすくなります。また、「次は必ず勝てる」という
ギャンブラーの誤謬に陥ることもあります。
(サイコロで5回連続で偶数が出ても、次が奇数になる確率は変わりません)この状態では、[�red]一旦トレードを休止し、冷静さを取り戻すことが最も重要です。
ナンピンは
プロスペクト理論の典型的な罠です。
含み損を認めたくない心理から、「平均取得価格を下げれば早く元に戻る」と考えて
ポジションを追加します。しかし、これは
損失を確定したくない感情に基づく非合理的な行動です。予想が外れたのに、さらに同じ方向に賭けるのは、
負けを認められない心理の表れです。
(カジノで負けた人が掛け金を増やすのと同じです)計画的でないナンピンは避けるべきです。
人が非合理的な行動をする理由は進化の過程で身につけた生存本能にあります。太古の昔、食料を失うことは生死に関わったため、損失を極度に恐れる性質が生き残りに有利でした。しかし、現代の金融市場では、この本能が逆に不利に働きます。また、脳は複雑な確率計算が苦手で、感情的な判断を優先しがちです。(直感は日常生活では役立ちますが、トレードでは邪魔になることが多いです)理性的な判断には、意識的な努力が必要です。
機関投資家も人間である以上、プロスペクト理論の影響から完全に逃れることはできません。ただし、個人投資家と比べて影響は小さくなります。その理由は、厳格なリスク管理ルールとチェック体制があるからです。また、アルゴリズム取引の活用により、感情的な判断を排除しています。(それでも、2008年の金融危機では多くの機関投資家が非合理的な行動を取りました)組織的なアプローチにより、心理的バイアスを最小限に抑えているのです。
プロスペクト理論を逆手に取るには
「多数派の心理を理解し、逆を行く」ことです。例えば、多くの人が
損切りできずに
含み損を抱えている価格帯は、強い
売り圧力となります。この
「痛みのポイント」を把握して取引することができます。また、
パニック売りが出やすいタイミングを狙う逆張り戦略も有効です。
(ただし、これには相当な経験と冷静さが必要です)他人の非合理的な行動を、自分の利益に変える視点が重要です。